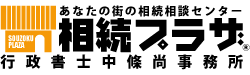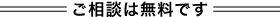渋沢栄一の『論語と算盤』の一節に、
「今の青年は、ただ学問のための学問をしている…」という言葉があります。
この言葉を読み、大学時代の自分自身の姿を思い出しました。将来何をするかも決めないまま大学に入り、目的意識を持たずに過ごしてしまった経験は、まさにこの指摘に重なります。
当時は、「進路は焦って決めるものではない」と軽く考えていました。
しかしこの考え方自体が、時代背景に甘えたものだったと、渋沢の言葉を通して気づかされました。
明治維新の直後、また戦後の混乱期には、国全体が生き延びるため、あるいは先進国に追いつくために、個々人が明確な目的を持ち、懸命に努力していました。
そうした時代では、「とりあえず大学へ」「進路は後で考える」といった発想は許されなかったはずです。
自分が進路に迷いながらも大学生活を送ることができたのは、先人たちの努力によって築かれた豊かさがあったからこそです。
この「豊かさの中にある無自覚な甘え」に気づくことができたのは、渋沢の言葉による大きな学びでした。
渋沢は、「分不相応な学問」が青年を誤らせ、国家の活力さえも奪うと警告しています。これは決して学問を否定しているのではなく、「目的のない学び」がいかに危険であるかを伝えています。
だからこそ、学ぶことは「何のために学ぶのか」を常に意識し、現実の生活や社会との接点を持って進める必要があるのです。
自らの仕事に対して目的意識を持ち続け、学び続け、社会に貢献できる力を身につけていくことが大切です。先陣への感謝を忘れず、日々の業務や学びに対して誠実に向き合い、社会のお役に立てるよう精進していきたいです。
※渋沢栄一が生きた時代背景が私の歴史認識と大きくことなることがわかりました。明治の初期を生きた人の社会の実態を知ることが出来ます。必読書です。